 寺院
寺院 「築地本願寺」
久しぶりに早朝に出かけました浄土真宗本願寺派 ご本尊は「阿弥陀如来」 (撮影が許されるお寺さんです)地下に続く階段で見られる動物の像をいつも見たくなります浄土宗本願寺派の直轄寺院、ゆっくりお参りさせていただきました1617年(元和3年)...
 寺院
寺院  イベント
イベント 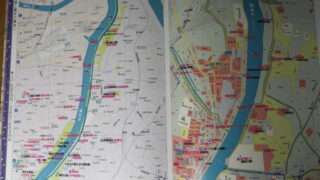 寺院
寺院  寺院
寺院  寺院
寺院