 美術館・博物館
美術館・博物館 続 「大浮世絵展」
浮世絵の「さらなる展開」喜多川歌麿、東洲斎写楽というスター浮世絵師の活躍したあと浮世絵はさらなる展開を見せる。色彩は華美となり、描写は誇張や歪曲が目立つようになってくる。描かれる対象も役者絵と美人画に、風景画が第三のジャンルとして加わり、さ...
 美術館・博物館
美術館・博物館  美術館・博物館
美術館・博物館 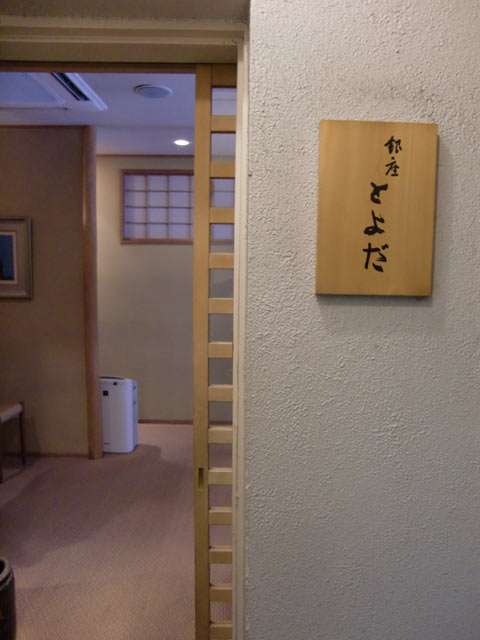 食べ歩き
食べ歩き  食べ歩き
食べ歩き  散策
散策