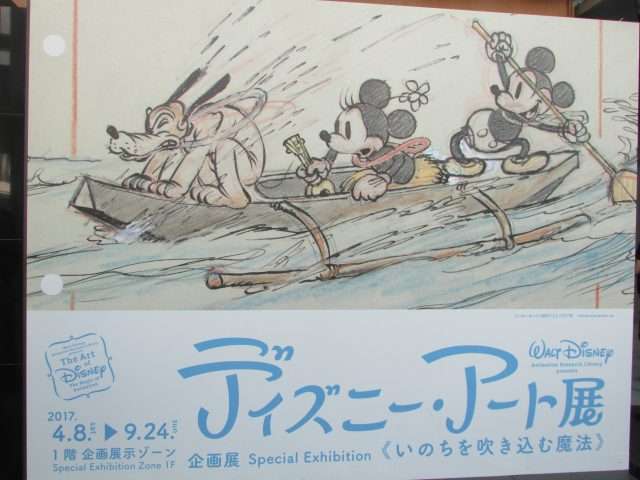 イベント
イベント ディズニー・アート展
同世代で小さい頃からデイズニーを楽しんでいた友人のTeiさんと出かけました。 1928年ウオルト・ディズニーは 「蒸気船ウイリー」を公開、1枚の絵に命を吹き込む魔法の歴史はここから始まりました。 「ピノキオ」は1940年の作品 描かれている...
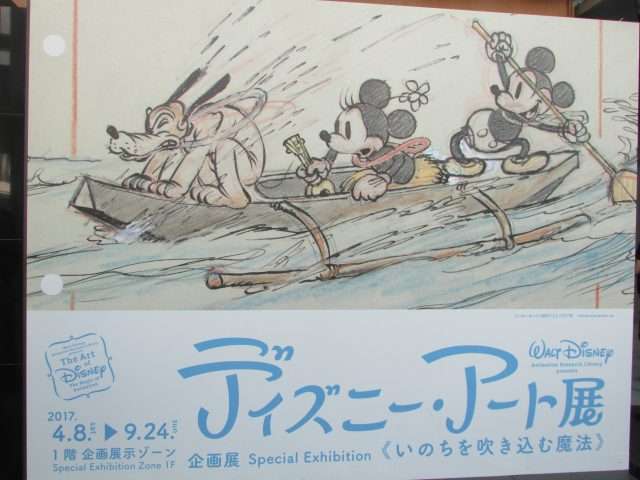 イベント
イベント  旅行
旅行  旅行
旅行  食べ歩き
食べ歩き  お祭
お祭