 神社
神社 「白山神社」の紫陽花
紫陽花の名所・東京十社・小石川鎮守,.文京区の「白山神社」に 今年も紫陽花を見に出かけました 手水舎もこの時期は紫陽花で飾られます 素敵でした 「拝殿」 まずはお参りさせていただきます 後ろ姿になってしまいましたが、江戸中期に奉納された狛...
 神社
神社 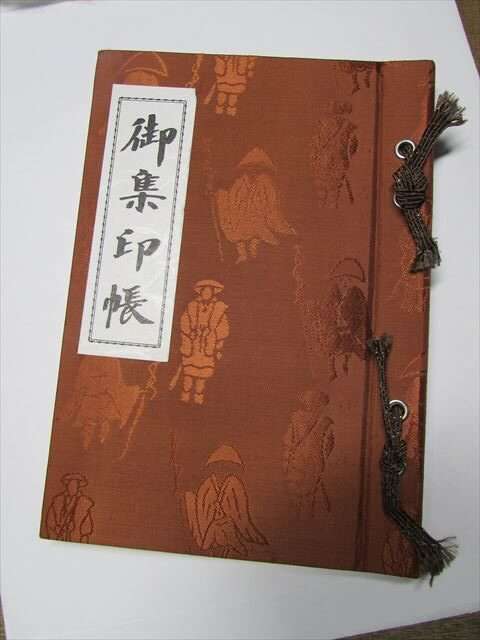 その他
その他  寺院
寺院  寺院
寺院  寺院
寺院