 公園・庭園
公園・庭園 「芝東照宮」と芝公園
芝公園は日本で最も古い公園のひとつだそうで、どこからでも東京タワーが間近に見えます、 明治6年に上野、浅草、深川、飛鳥山と供に芝の5か所が、日本で最初の公園として指定され、 以後公園造成の先駆けとなりました 当時は増上寺の境内を含む広い公園...
 公園・庭園
公園・庭園  寺院
寺院  散策
散策 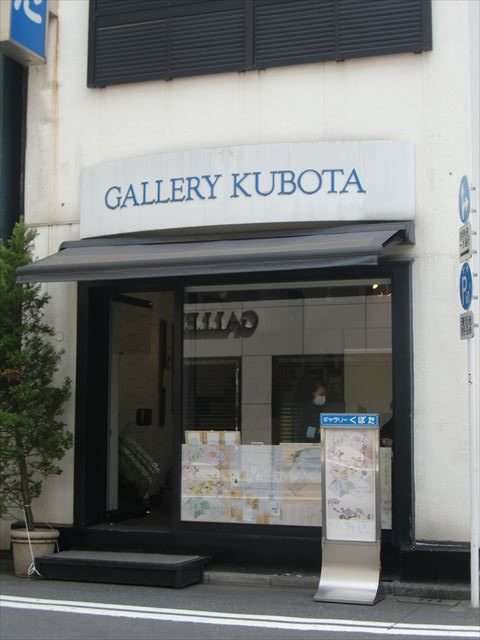 イベント
イベント  寺院
寺院